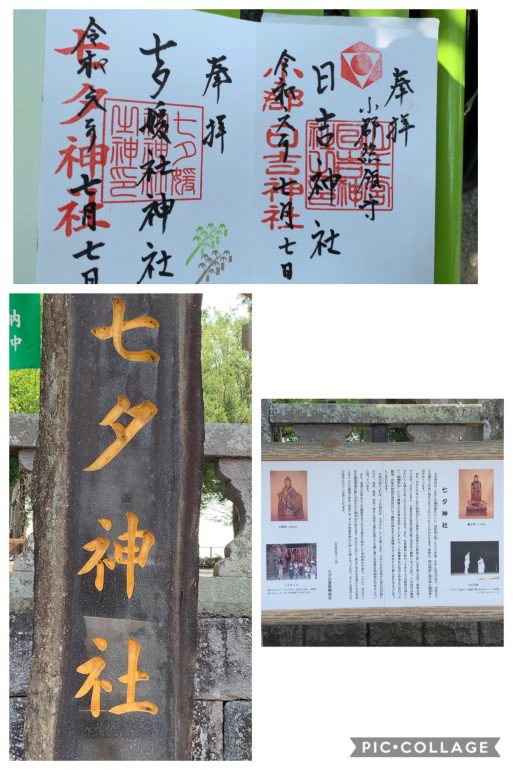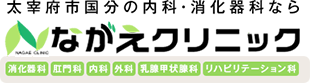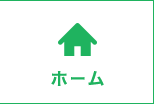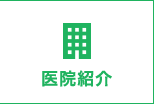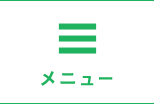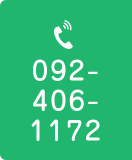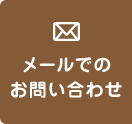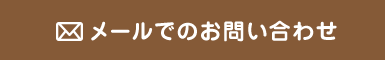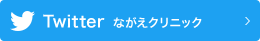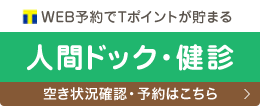2019.08.01
夏がやってきました
今日から8月 どんどんと暑くなってきました。
どんどんと暑くなってきました。
梅雨が明けたと思えば気温がグンッと上がりましたね
通り雨も最近では多め。蒸し暑さたまらないですね。
蝉も元気に朝から鳴いています 本格的な夏やってきました
本格的な夏やってきました
熱中症、ニュースでもよく見ます。
こまめに水分補給をしましょう。
最近の夕方は空が綺麗です。どうでしょうこの写真
紫とオレンジと水色、中々見ることのできない空ですね
お気に入りの一枚を皆さんにお裾分けです。どうぞっ

事務:K.M
2019.07.18
夏祭り
雨の日が続いてはいますが、
蝉の鳴き声に夏を感じています。
一日中晴れると30度を超え、
帽子や日傘があっても、
日差しが痛いくらいでした。
これからお祭りシーズンですね。
もう行かれた方もこれからの方も、
マナーを守って楽しく過ごしましょう。
梅雨明けが待ち遠しいですが、
体調管理にお気を付けて。
事務:C.H
2019.07.08
七夕
昨日は、七夕でしたね
私は電車に乗って、一人旅をしてきました。
昨日の我が家はそれぞれの予定があったので、
一人で何をしようかな?なんて考えていたら
「七夕」の付く所はないかなと探していたら
小郡にありました。
「七夕神社」
沢山の方が参拝に来ていましたよ(^^)
私も参拝を済ませて、御朱印を頂いてきました。
さて、昨日は織姫と彦星は逢うことが出来たのでしょうか?
事務:R.N